ごあいさつ
会長のごあいさつ
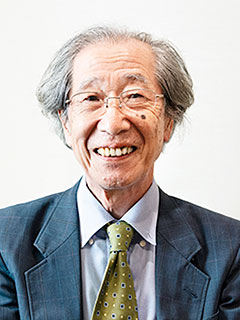
甘利 俊一
公益財団法人 日本数学検定協会 会長
理化学研究所 栄誉研究員
東京大学 名誉教授
数学はおもしろい、夢中になってしまう、これがみなさんの感想ではないでしょうか。私もそうです。だから、人類は古代から数学を作ってきたのでした。ギリシャで、中国で、アラビアで、インドで、数学は生まれ育ちました。日本でも江戸時代の和算は相当のレベルに到達したのです。
これは、脳のなせる技です。人の脳はいつのまにか、数学的な思考をするように発展したのです。これは、言語をあやつり、概念を作り、関係を調べる、こうした能力と同じ根を持ちます。
人類は、社会生活のなかでこの能力を培ってきました。仲間との共同作業にはコミュニケーションが必要で、そのためには自分の意図を自分で知り、相手の意図を理解する心が必要です。心、意識、言語、数学など、みな同じ脳の産物です。数学は知の体系として文明社会で確立し、発展してきています。数学的に考えることは楽しい。それなのに、世の中には数学嫌いも多い。これはなぜでしょうか。
学習の課題が年次ごとに設定され、教育課程として固定化し、試験の対象となってしまった。これは、社会のシステムとして、やむをえないのかもしれない。でも、これが数学をじっくりと考える楽しみを奪い、解き方を知識として暗記し、すばやく応答するという技に変えてしまった。脳はそのような暗記はきらいです。考えることが好きなのです。
数学はこれを職業とする純粋数学者のためのものであり、他の人々は受験科目として耐え忍び、時には点を稼ぐのに効率の良い科目であるなどという誤解が拡がります。だから、2次方程式の解法など教える必要はない、日常生活でそんなものは使ったこともない、などという評論をする有名人が現れます。
数学は受験のためのものでしょうか。とんでもない、人間の本性に根ざす、考える喜び、ものごとを筋道を立てて整理し、推論し、解を求める喜びにあるのです。だから、数学者にならない人でも、理科系はもちろんのこと、文科系の人たちにも、数学の素養が必要で、その楽しさを知ることが役に立つのです。これは人類の築いた文化なのです。
初代の一松信会長、次代の秋山仁会長に続いて、私が三代めの会長に推挙されました。たいへん重い役ですが、数学の好きな私にとって、このような喜ばしい仕事を晩年にできることは身に余る光栄です。
皆さんとともに、数学の楽しさを味わい、同志を拡める道を進んでゆきましょう。
理事長のごあいさつ

髙田 忍
公益財団法人 日本数学検定協会 理事長
「60%の壁」。この言葉を聞いて、みなさまは何を思い浮かべるでしょうか。
国の行う全国学力・学習状況調査では毎年、中学生に「数学の勉強は好きですか」と質問しています。先の数は、その回答に「当てはまる」または「どちらかといえば、当てはまる」と答えた生徒の割合です。実は、2007(平成19)年度以降の調査において、これが全体の60%を超えたことはありません。しかし、教育現場で学びの質や深まりを重視したくふうを日々積み重ねられたおかげで、その割合は徐々に高まり、2022年度にはついに58.3%に達し、60%を超えるのも遠い未来ではありません。これまでご尽力されたすべての関係者のみなさまに敬意を表します。そしてもう1つ、ここに興味深い結果があります。それは「算数・数学の勉強は大切だと思いますか」「算数・数学の授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役立つと思いますか」の質問に対して、肯定する回答が毎年とても高い割合で得られ続けていることです。なぜ、子どもたちはそう思っているのでしょうか。私は、子どもたちが日常生活や学校教育のなかで、社会情勢と学びの指針を感じ取っているからだと推察しています。
日本の社会では、社会課題解決型ビジネスが注目されています。Society5.0の実現に向けて、AI(人工知能)、ビッグデータ、IoT(Internet of Things)などが急速に進化し、それらを活用して社会課題を解決するデータサイエンス人材やDX(デジタルトランスフォーメーション)人材の確保が急務となりました。そして現在は、人材の育成が重要視されています。2022年4月に政府が発表した「AI戦略2022」では「第四部『すべてにAI』を目指した着実な取組」において、6つの取り組みを推進するとしました。そこで最初に掲げたのが、教育改革です。改革には「まずは、さまざまな社会課題と数学・理科の関係を早い段階からしっかりと理解し、数学・理科の力で解決する思考の経験が肝要である」と述べています。文部科学省も、課題を解決していくための力の育成が社会的な要請となっていることを従来から認識し「目の前の事象から解決すべき課題を見いだし、主体的に考え、多様な立場の者が協働的に議論し、納得解を生み出す資質・能力が一層強く求められている」として、令和の日本型学校教育の構築に注力しています(中央教育審議会答申「令和の日本型学校教育の構築を目指して」(2021.1))。
公益財団法人日本数学検定協会(以下「当協会」)は、生涯学習の観点で数学に関する事業をいくつも展開しており、まさに生涯にわたって人が成長し続けることをサポートしています。実用数学技能検定「数検」は、学校などの公教育、塾などの民間教育、家族の支えによる家庭教育、そして、自己の能力向上をめざす社会教育にいたるまで、幅広いシーンで活用されてきました。2022年3月に累計のべ志願者数が700万人を突破したのも、ひとえに受検者ならびにかれらを支えてくださった多くのみなさまのご支援の賜物と感謝申し上げます。また、学校で学んだ数学力をビジネスの現場で生かすために必要な考え方・使い方を身につける「ビジネス数学」、データサイエンスの基盤となる基礎的な数学力とそれを活用するコンサルティング力を兼ね備えた専門家として認定する資格「データサイエンス数学ストラテジスト」においても、みなさまのご愛顧とご支援を賜り重ねて御礼申し上げます。当協会の使命の1つは、課題を解決していくために必要な基礎力の1つである算数・数学の学びの機会を、あらゆる世代に提供することです。そのため当協会は、これまで以上に社会のニーズに積極的に応えていかなくてはなりません。検定事業の枠にとどまらず、生涯学習の算数・数学の学びの面で「人を育てる」ことをめざして挑戦し続けます。
受検者ならびに広く国民のみなさまにとって一層有益なものとなるよう、これまで実施してきた諸事業を改革するとともに、新たな事業の創出も視野に入れて公益に応えていくことが必要であると考えています。みなさまのこれまでの温かいご指導とご鞭撻に感謝し、これからも引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げ、あいさつといたします。
