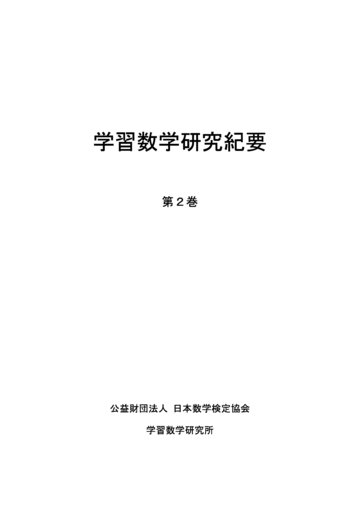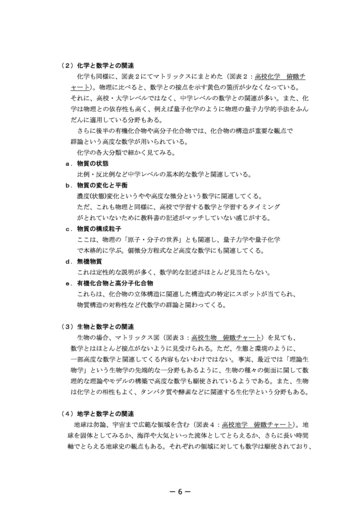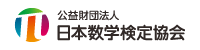 学習数学研究紀要 創刊号(第2巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第2巻)
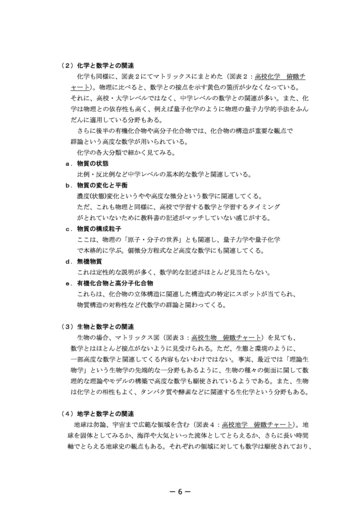
- ページ: 9
- (2)化学と数学との関連 化学も同様に、図表2にてマトリックスにまとめた(図表2:高校化学 俯瞰チ ャート) 。物理に比べると、数学との接点を示す黄色の箇所が少なくなっている。 それに、高校・大学レベルではなく、中学レベルの数学との関連が多い。また、化 学は物理との依存性も高く、例えば量子化学のように物理の量子力学的手法をふん だんに適用している分野もある。 さらに後半の有機化合物や高分子化合物では、化合物の構造が重要な観点で 群論という高度な数学が用いられている。 化学の各大分類で細かく見てみる。 a.物質の状態 比例・反比例など中学レベルの基本的な数学と関連している。 b.物質の変化と平衡 濃度(状態)変化というやや高度な微分という数学に関連してくる。 ただ、これも物理と同様に、高校で学習する数学と学習するタイミング がとれていないために教科書の記述がマッチしていない感じがする。 c.物質の構成粒子 ここは、物理の「原子・分子の世界」とも関連し、量子力学や量子化学 で本格的に学ぶ。偏微分方程式など高度な数学にも関連してくる。 d.無機物質 これは定性的な説明が多く、数学的な記述がほとんど見当たらない。 e.有機化合物と高分子化合物 これらは、化合物の立体構造に関連した構造式の特定にスポットが当てられ、 物質構造の対称性など代数学の群論と関わってくる。 (3)生物と数学との関連 生物の場合、マトリックス図(図表3:高校生物 俯瞰チャート)を見ても、 数学とはほとんど接点がないように見受けられる。ただ、生態と環境のように、 一部高度な数学と関連してくる内容もないわけではない。事実、最近では「理論生 物学」という生物学の先端的な一分野もあるように、生物の種々の側面に関して数 理的な理論やモデルの構築で高度な数学も駆使されているようである。また、生物 は化学との相性もよく、タンパク質や酵素などに関連する生化学という分野もある。 (4)地学と数学との関連 地球は勿論、宇宙まで広範な領域を含む(図表4:高校地学 俯瞰チャート) 。地 球を固体としてみるか、海洋や大気といった流体としてとらえるか、さらに長い時間 軸でとらえる地球史の観点もある。それぞれの領域に対しても数学は駆使されており、
- 6 -
�
- ▲TOP
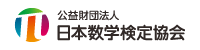 学習数学研究紀要 創刊号(第2巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第2巻)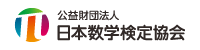 学習数学研究紀要 創刊号(第2巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第2巻)