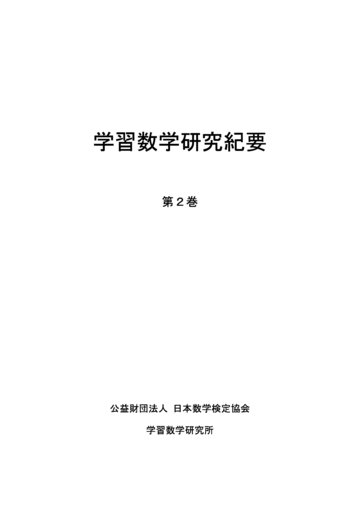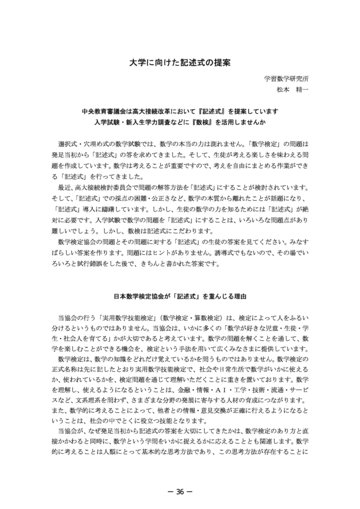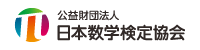 学習数学研究紀要 創刊号(第2巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第2巻)
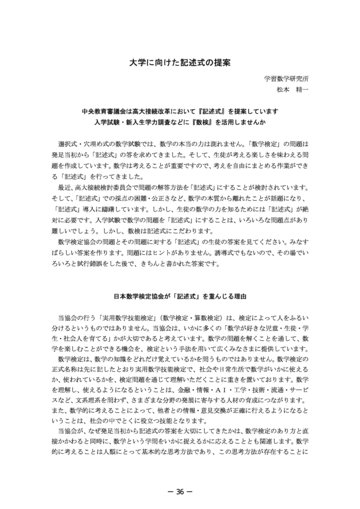
- ページ: 40
- 大学に向けた記述式の提案
学習数学研究所 松本 精一 中央教育審議会は高大接続改革において『記述式』を提案しています 入学試験・新入生学力調査などに『数検』を活用しませんか 選択式・穴埋め式の数学試験では、数学の本当の力は測れません。 「数学検定」の問題は 発足当初から「記述式」の答を求めてきました。そして、生徒が考える楽しさを味わえる問 題を作成しています。 数学は考えることが重要ですので、 考えを自由にまとめる作業ができ る「記述式」を行ってきました。 最近、 高大接続検討委員会で問題の解答方法を 「記述式」 にすることが検討されています。 そして、 「記述式」 での採点の困難・公正さなど、 数学の本質から離れたことが話題になり、 「記述式」導入に躊躇しています。しかし、生徒の数学の力を知るためには「記述式」が絶 対に必要です。入学試験で数学の問題を「記述式」にすることは、いろいろな問題点があり 難しいでしょう。しかし、数検は記述式にこだわります。 数学検定協会の問題とその問題に対する「記述式」の生徒の答案を見てください。みなす ばらしい答案を作ります。問題にはヒントがありません。誘導式でもないので、その場でい ろいろと試行錯誤をした後で、きちんと書かれた答案です。
日本数学検定協会が「記述式」を重んじる理由 当協会の行う「実用数学技能検定」 (数学検定・算数検定)は、検定によって人をふるい 分けるというものではありません。当協会は、いかに多くの「数学が好きな児童・生徒・学 生・社会人を育てる」かが大切であると考えています。数学の問題を解くことを通して、数 学を楽しむことができる機会を、検定という手法を用いて広くみなさまに提供しています。 数学検定は、 数学の知識をどれだけ覚えているかを問うものではありません。 数学検定の 正式名称は先に記したとおり実用数学技能検定で、社会や日常生活で数学がいかに使える か、使われているかを、検定問題を通じて理解いただくことに重きを置いております。数学 を理解し、使えるようになるということは、金融・情報・AI・工学・技術・流通・サービ スなど、 文系理系を問わず、 さまざまな分野の発展に寄与する人材の育成につながります。 また、数学的に考えることによって、他者との情報・意見交換が正確に行えるようになると いうことは、社会の中でとくに役立つ技能となります。 当協会が、 なぜ発足当初から記述式の答案を大切にしてきたかは、 数学検定のあり方と直 接かかわると同時に、 数学という学問をいかに捉えるかに応えることとも関連します。 数学 的に考えることは人類にとって基本的な思考方法であり、この思考方法が存在することに
- 36 -
�
- ▲TOP
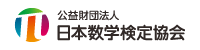 学習数学研究紀要 創刊号(第2巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第2巻)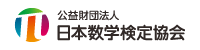 学習数学研究紀要 創刊号(第2巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第2巻)