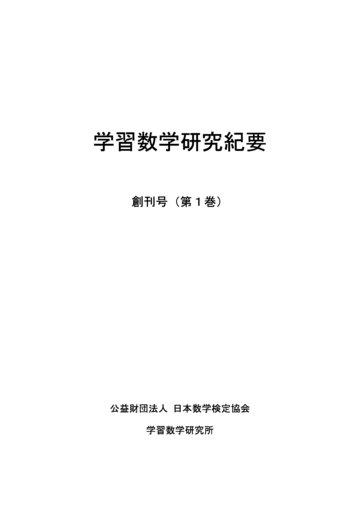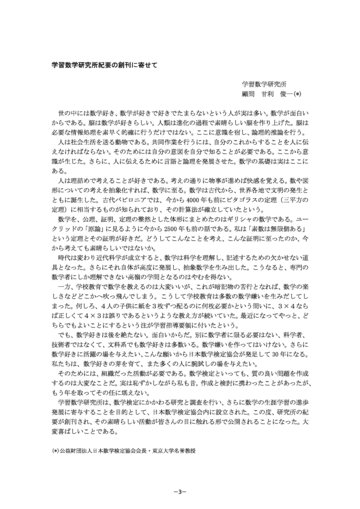学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
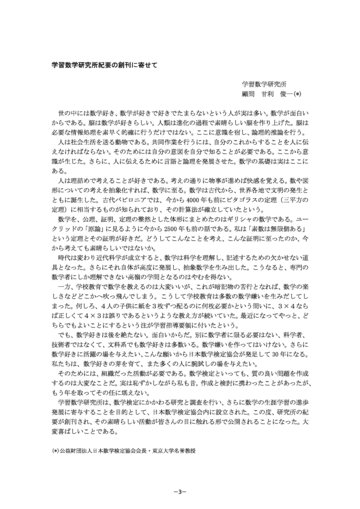
- ページ: 5
- 学習数学研究所紀要の創刊に寄せて
学習数学研究所 顧問 甘利 俊一(*) 世の中には数学好き、 数学が好きで好きでたまらないという人が実は多い。 数学が面白い からである。脳は数学が好きらしい。人類は進化の過程で素晴らしい脳を作り上げた。脳は 必要な情報処理を素早く的確に行うだけではない。 ここに意識を宿し、 論理的推論を行う。 人は社会生活を送る動物である。 共同作業を行うには、 自分のこれからすることを人に伝 えなければならない。 そのためには自分の意図を自分で知ることが必要である。 ここから意 識が生じた。さらに、人に伝えるために言語と論理を発展させた。数学の基礎は実はここに ある。 人は理詰めで考えることが好きである。 考えの通りに物事が進めば快感を覚える。 数や図 形についての考えを抽象化すれば、数学に至る。数学は古代から、世界各地で文明の発生と ともに誕生した。古代バビロニアでは、今から 4000 年も前にピタゴラスの定理(三平方の 定理)に相当するものが知られており、その計算法が確立していたという。 数学を、公理、証明、定理の整然とした体形にまとめたのはギリシャの数学である。ユー クリッドの 「原論」 に見るように今から 2500 年も前の話である。 私は 「素数は無限個ある」 という定理とその証明が好きだ。どうしてこんなことを考え、こんな証明に至ったのか、今 から考えても素晴らしいではないか。 時代は変わり近代科学が成立すると、 数学は科学を理解し、 記述するための欠かせない道 具となった。さらにそれ自体が高度に発展し、抽象数学を生み出した。こうなると、専門の 数学者にしか理解できない高嶺の学問となるのはやむを得ない。 一方、学校教育で数学を教えるのは大変いいが、これが暗記物の苦行となれば、数学の楽 しさなどどこかへ吹っ飛んでしまう。こうして学校教育は多数の数学嫌いを生みだしてし まった。何しろ、4人の子供に紙を3枚ずつ配るのに何枚必要かという問いに、3×4なら ば正しくて4×3は誤りであるというような教え方が続いていた。 最近になってやっと、 ど ちらでもよいことにするという注が学習指導要領に付いたという。 でも、数学好きは後を絶たない。面白いからだ。別に数学者に限る必要はない、科学者、 技術者ではなくて、文科系でも数学好きは多数いる。数学嫌いを作ってはいけない。さらに 数学好きに活躍の場を与えたい、 こんな願いから日本数学検定協会が発足して 30 年になる。 私たちは、数学好きの芽を育て、また多くの人に腕試しの場を与えたい。 そのためには、組織だった活動が必要である。数学検定といっても、質の良い問題を作成 するのは大変なことだ。 実は恥ずかしながら私も昔, 作成と検討に携わったことがあったが、 もう年を取ってその任に堪えない。 学習数学研究所は、 数学検定にかかわる研究と調査を行い、 さらに数学の生涯学習の進歩 発展に寄与することを目的として、日本数学検定協会内に設立された。この度、研究所の紀 要が創刊され、 その素晴らしい活動が皆さんの目に触れる形で公開されることになった。 大 変喜ばしいことである。
(*)公益財団法人日本数学検定協会会長・東京大学名誉教授
-3-
�
- ▲TOP
 学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第1巻) 学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)