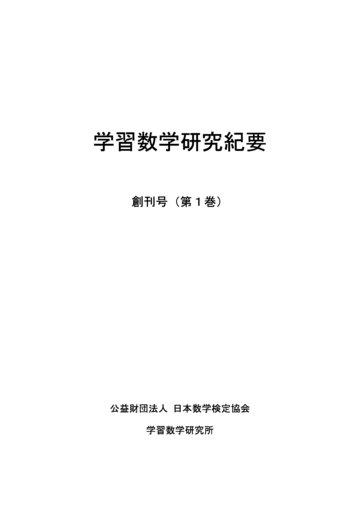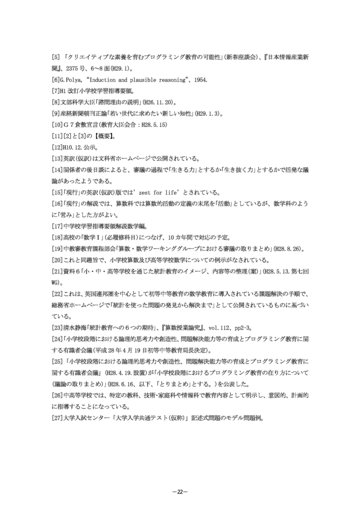学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
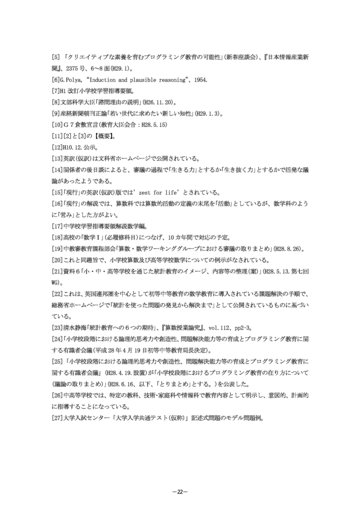
- ページ: 25
- [5] 「クリエイティブな素養を育むプログラミング教育の可能性」(新春座談会)、 『日本情報産業新 聞』 、2375 号、6~8 面(H29.1)。 [6]G.Polya,“Induction and plausible reasoning” 、1954. [7]H1 改訂小学校学習指導要領。 [8]文部科学大臣「諮問理由の説明」(H26.11.20)。 [9]産経新聞朝刊正論「若い世代に求めたい新しい知性」(H29.1.3)。 [10]G7倉敷宣言(教育大臣会合:H28.5.15) [11][2]と[3]の【概要】 。 [12]H10.12.公示。 [13]英訳(仮訳)は文科省ホームページで公開されている。 [14]関係者の後日談によると、審議の過程で「生きる力」とするか「生き抜く力」とするかで活発な議 論があったようである。 [15]「現行」の英訳(仮訳)版では’zest for life’とされている。 [16]「現行」の解説では、算数科では算数的活動の定義の末尾を「活動」としているが、数学科のよう に「営み」とした方がよい。 [17]中学校学習指導要領解説数学編。 [18]高校の「数学Ⅰ」(必履修科目)につなげ、10 カ年間で対応の予定。 [19]中教審教育課程部会「算数・数学ワーキンググループにおける審議の取りまとめ」(H28.8.26)。 [20]これと同趣旨で、小学校算数及び高等学校数学についての例示がなされている。 [21]資料6「小・中・高等学校を通じた統計教育のイメージ、内容等の整理(案)」(H28.5.13.第七回 WG)。 [22]これは、 英国連邦圏を中心として初等中等教育の数学教育に導入されている課題解決の手順で、 総務省ホームページで「統計を使った問題の発見から解決まで」として公開されているものに基づい ている。 [23]清水静海「統計教育への6つの期待」、 『算数授業論究』 、vol.112、pp2-3。 [24]「小学校段階における論理的思考力や創造性、 問題解決能力等の育成とプログラミング教育に関 する有識者会議(平成 28 年 4 月 19 日初等中等教育局長決定)。 [25]「小学校段階における論理的思考力や創造性、問題解決能力等の育成とプログラミング教育に 関する有識者会議」(H28.4.19.設置)が「小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について (議論の取りまとめ)」(H28.6.16、以下、「とりまとめ」とする。)を公表した。 [26]中高等学校では、特定の教科、技術・家庭科や情報科で教育内容として明示し、意図的、計画的 に指導することになっている。 [27]大学入試センター「大学入学共通テスト(仮称)」記述式問題のモデル問題例。
-22-
�
- ▲TOP
 学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第1巻) 学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)