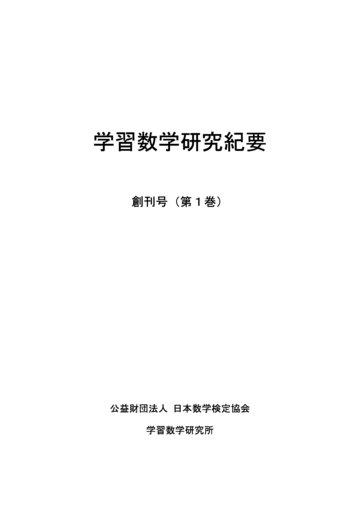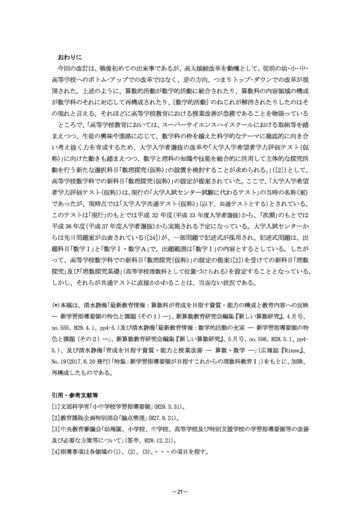学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
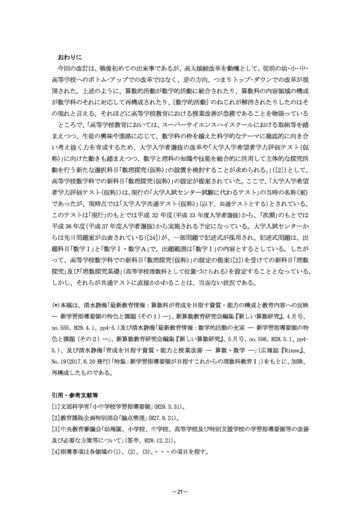
- ページ: 24
- おわりに 今回の改訂は、 戦後初めての出来事であるが、高大接続改革を動機として、 従前の幼・小・中・ 高等学校へのボトム・アップでの改革ではなく、逆の方向、つまりトップ・ダウンでの改革が展 開された。上述のように、算数的活動が数学的活動に統合されたり、算数科の内容領域の構成 が数学科のそれに対応して再構成されたり、 〔数学的活動〕 のねじれが解消されたりしたのはそ の現れと言える。それほどに高等学校教育における授業改善が急務であることを物語っている ところで、 「高等学校教育においては、 スーパーサイエンスハイスクールにおける取組等を踏 まえつつ、生徒の興味や進路に応じて、数学科の枠を越えた科学的なテーマに徹底的に向き合 い考え抜く力を育成するため、大学入学者選抜の改革や「大学入学希望者学力評価テスト(仮 称)」に向けた動きも踏まえつつ、数学と理科の知識や技能を総合的に活用して主体的な探究活 動を行う新たな選択科目「数理探究(仮称)」の設置を検討することが求められる。 」([2])として、 高等学校数学科での新科目「数理探究(仮称)」の設定が提案されていた。 ここで、 「大学入学希望 者学力評価テスト(仮称) )は、 現行の「大学入試センター試験に代わるテスト」の当時の名称(案) であったが、現時点では「大学入学共通テスト(仮称)」(以下、共通テストとする)とされている。 このテストは「現行」のもとでは平成 32 年度(平成 33 年度入学者選抜)から、「次期」のもとでは 平成 36 年度(平成 37 年度入学者選抜)から実施される予定になっている。大学入試センターか らは先日問題案が公表されている([24])が、一部問題で記述式が採用され、記述式問題は、出 題科目「数学Ⅰ」と「数学Ⅰ・数学A」で、出題範囲は「数学Ⅰ」の内容とするとしている。したが って、高等学校数学科での新科目「数理探究(仮称)」の設定の提案([2])を受けての新科目「理数 探究」及び「理数探究基礎」(高等学校理数科として位置づけられる)を設定することとなっている。 しかし、それらが共通テストに直接かかわることは、当面ない状況である。
(*)本稿は、清水静海「最新教育情報:算数科が育成を目指す資質・能力の構成と教育内容への反映 ― 新学習指導要領の特色と課題 (その1) ―」 、 新算数教育研究会編集 『新しい算数研究』 、 4 月号、 no.555、H29.4.1、pp4-5.)及び清水静海「最新教育情報:数学的活動の充実 ― 新学習指導要領の特 色と課題(その2)―」、新算数教育研究会編集『新しい算数研究』 、5 月号、no.556、H29.5.1、pp45.)、及び清水静海「育成を目指す資質・能力と授業改善 ― 算数・数学 ―」(広報誌『Rimse』 、 No.19(2017.6.20 発行)「特集:新学習指導要領が目指すこれからの理数科教育Ⅰ」)をもとに、 加除、 再構成したものである。
引用・参考文献等 [1]文部科学省「小中学校学習指導要領」(H29.3.31)。 [2]教育課程企画特別部会「論点整理」(H27.8.21)。 [3]中央教育審議会「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善 及び必要な方策等について」(答申、H28.12.21)。 [4]指導事項は各領域の(1)、(2)、(3)、 ・・・の項目を指す。
-21-
�
- ▲TOP
 学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第1巻) 学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)