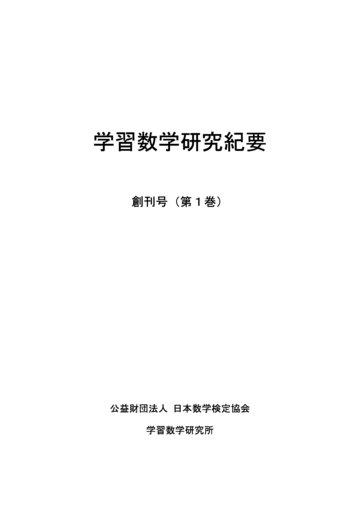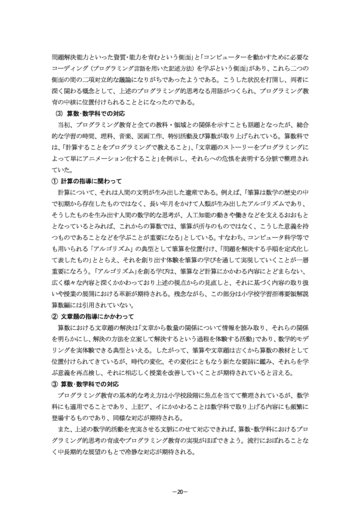学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
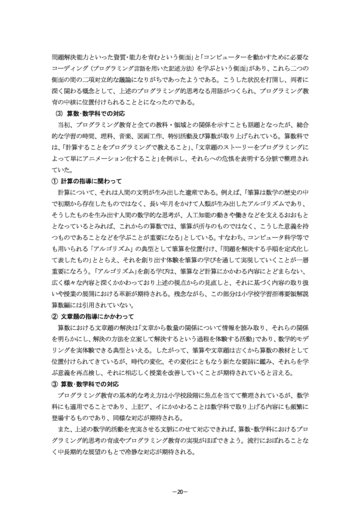
- ページ: 23
- 問題解決能力といった資質・能力を育むという側面」と「コンピューターを動かすために必要な コーディング (プログラミング言語を用いた記述方法) を学ぶという側面」があり、 これら二つの 側面の間の二項対立的な議論になりがちであったようである。こうした状況を打開し、両者に 深く関わる概念として、上述のプログラミング的思考なる用語がつくられ、プログラミング教 育の中核に位置付けられることとになったのである。 (3) 算数・数学科での対応 当初、プログラミング教育と全ての教科・領域との関係を示すことも話題となったが、総合 的な学習の時間、理科、音楽、図画工作、特別活動及び算数が取り上げられている。算数科で は、 「計算することをプログラミングで教えること」、 「文章題のストーリーをプログラミングに よって単にアニメーション化すること」を例示し、それらへの危惧を表明する分脈で整理され ていた。 ① 計算の指導に関わって 計算について、 それは人間の文明が生み出した遺産である。例えば、「筆算は数学の歴史の中 で初期から存在したものではなく、長い年月をかけて人類が生み出したアルゴリズムであり、 そうしたものを生み出す人間の数学的な思考が、人工知能の動きや働きなどを支えるおおもと となっているとみれば、これからの算数では、筆算が所与のものではなく、こうした意義を持 つものであることなどを学ぶことが重要になる」としている。 すなわち、 コンピュータ科学等で も用いられる「アルゴリズム」 の典型として筆算を位置付け、「問題を解決する手順を定式化し て表したもの」ととらえ、それを創り出す体験を筆算の学びを通して実現していくことが一層 重要になろう。「アルゴリズム」を創る学びは、筆算など計算にかかわる内容にとどまらない、 広く様々な内容と深くかかわっており上述の視点からの見直しと、それに基づく内容の取り扱 いや授業の展開における革新が期待される。残念ながら、この部分は小学校学習指導要領解説 算数編には引用されていない。 ② 文章題の指導にかかわって 算数における文章題の解決は「文章から数量の関係について情報を読み取り、それらの関係 を明らかにし、 解決の方法を立案して解決するという過程を体験する活動」であり、 数学的モデ リングを実体験できる典型といえる。したがって、筆算や文章題は古くから算数の教材として 位置付けられてきているが、時代の変化、その変化にともなう新たな要請に鑑み、それらを学 ぶ意義を再点検し、それに相応しく授業を改善していくことが期待されていると言える。 ③ 算数・数学科での対応 プログラミング教育の基本的な考え方は小学校段階に焦点を当てて整理されているが、数学 科にも適用でることであり、上記ア、イにかかわることは数学科で取り上げる内容にも頻繁に 登場するものであり、同様な対応が期待される。 また、 上述の数学的活動を充実させる文脈にのせて対応できれば、 算数・数学科におけるプロ グラミング的思考の育成やプログラミング教育の実現がほぼできよう。流行におぼれることな く中長期的な展望のもとで冷静な対応が期待される。
-20-
�
- ▲TOP
 学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第1巻) 学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)