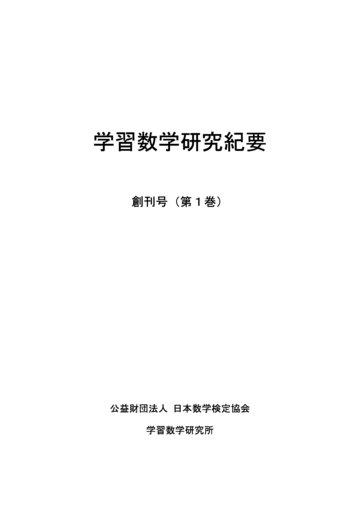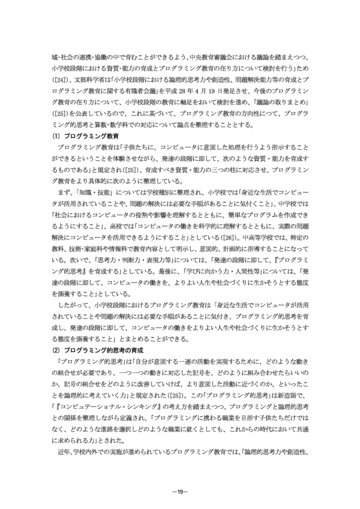学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
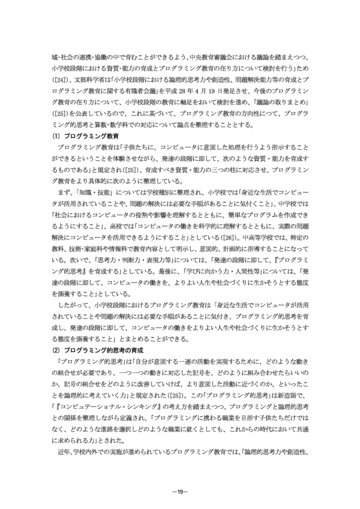
- ページ: 22
- 域・社会の連携・協働の中で育むことができるよう、 中央教育審議会における議論を踏まえつつ、 小学校段階における資質・能力の育成とプログラミング教育の在り方について検討を行う」ため
([24])、 文部科学省は「小学校段階における論理的思考力や創造性、 問題解決能力等の育成とプ
ログラミング教育に関する有識者会議」を平成 28 年 4 月 19 日発足させ、今後のプログラミン グ教育の在り方について、小学校段階の教育に軸足をおいて検討を進め、「議論の取りまとめ」
([25])を公表しているので、これに基づいて、プログラミング教育の方向性につて、プログラ
ミング的思考と算数・数学科での対応について論点を整理することとする。 (1) プログラミング教育 プログラミング教育は「子供たちに、コンピュータに意図した処理を行うよう指示すること ができるということを体験させながら、発達の段階に即して、次のような資質・能力を育成す るものである」と規定され([25])、育成すべき資質・能力の三つの柱に対応させ、プログラミン グ教育をより具体的に次のように整理している。 まず、 「知識・技能」については学校種別に整理され、小学校では「身近な生活でコンピュー タが活用されていることや、 問題の解決には必要な手順があることに気付くこと」、 中学校では 「社会におけるコンピュータの役割や影響を理解するとともに、簡単なプログラムを作成でき るようにすること」、高校では「コンピュータの働きを科学的に理解するとともに、実際の問題 解決にコンピュータを活用できるようにすること」としている([26])。 中高等学校では、 特定の 教科、 技術・家庭科や情報科で教育内容として明示し、意図的、 計画的に指導することになって いる。次いで、「思考力・判断力・表現力等」については、「発達の段階に即して、 『プログラミ ング的思考』を育成する」としている。最後に、「学びに向かう力・人間性等」については、「発 達の段階に即して、コンピュータの働きを、よりよい人生や社会づくりに生かそうとする態度 を涵養すること」としている。 したがって、小学校段階におけるプログラミング教育は「身近な生活でコンピュータが活用 されていることや問題の解決には必要な手順があることに気付き、プログラミング的思考を育 成し、発達の段階に即して、コンピュータの働きをよりよい人生や社会づくりに生かそうとす る態度を涵養すること」とまとめることができる。 (2) プログラミング的思考の育成 「プログラミング的思考」は「自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動き の組合せが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいの か、記号の組合せをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったこ とを論理的に考えていく力」と規定された([25])。この「プログラミング的思考」は新造語で、 「『コンピュテーショナル・シンキング』の考え方を踏まえつつ、プログラミングと論理的思考 との関係を整理しながら定義され、「プログラミングに携わる職業を目指す子供たちだけでは なく、どのような進路を選択しどのような職業に就くとしても、これからの時代において共通 に求められる力」とされた。 近年、 学校内外での実施が進められているプログラミング教育では、 「論理的思考力や創造性、
-19-
�
- ▲TOP
 学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第1巻) 学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)