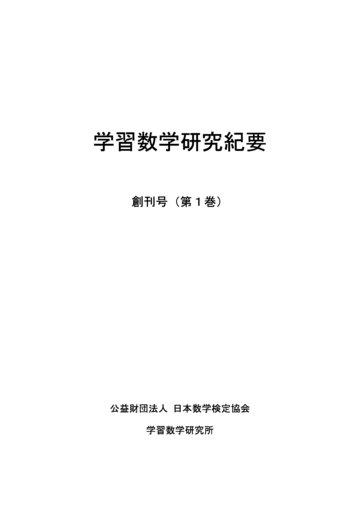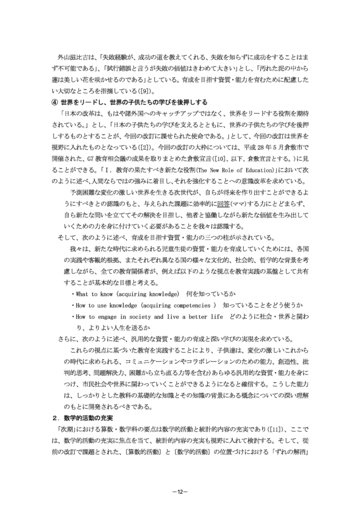学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
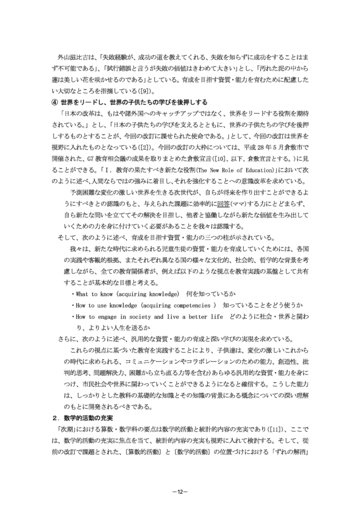
- ページ: 15
- 外山滋比古は、「失敗経験が、 成功の道を教えてくれる、 失敗を知らずに成功をすることはま ず不可能である」、「試行錯誤と言うが失敗の価値はきわめて大きい」とし、「汚れた泥の中から 蓮は美しい花を咲かせるのである」としている。 育成を目指す資質・能力を育むために配慮した い大切なところを指摘している([9])。 ④ 世界をリードし、世界の子供たちの学びを後押しする 「日本の改革は、もはや諸外国へのキャッチアップではなく、世界をリードする役割を期待 されている。 」とし、「日本の子供たちの学びを支えるとともに、世界の子供たちの学びを後押 しするものとすることが、 今回の改訂に課せられた使命である。」として、今回の改訂は世界を 視野に入れたものとなっている([2])。今回の改訂の大枠については、平成 28 年 5 月倉敷市で 開催された、G7 教育相会議の成果を取りまとめた倉敷宣言([10]、以下、倉敷宣言とする。)に見 ることができる。「Ⅰ.教育の果たすべき新たな役割(The New Role of Education)」において次 のように述べ、 人間ならではの強みに着目し、 それを強化することへの意識改革を求めている。 予測困難な変化の激しい世界を生きる次世代が、自らが将来を作り出すことができるよ うにすべきとの認識のもと、与えられた課題に効率的に回答(ママ)する力にとどまらず、 自ら新たな問いを立ててその解決を目指し、他者と協働しながら新たな価値を生み出して いくための力を身に付けていく必要があることを我々は認識する。 そして、次のように述べ、育成を目指す資質・能力の三つの柱が示されている。 我々は、新たな時代に求められる児童生徒の資質・能力を育成していくためには、各国 の実践や客観的根拠、またそれぞれ異なる国の様々な文化的、社会的、哲学的な背景を考 慮しながら、全ての教育関係者が、例えば以下のような視点を教育実践の基盤として共有 することが基本的な目標と考える。 ・What to know (acquiring knowledge) 何を知っているか ・How to use knowledge (acquiring competencies ) 知っていることをどう使うか ・How to engage in society and live a better life どのように社会・世界と関わ り、よりよい人生を送るか さらに、次のように述べ、汎用的な資質・能力の育成と深い学びの実現を求めている。 これらの視点に基づいた教育を実践することにより、子供達は、変化の激しいこれから の時代に求められる、コミュニケーションやコラボレーションのための能力、創造性、批 判的思考、 問題解決力、 困難から立ち直る力等を含む)あらゆる汎用的な資質・能力を身に つけ、市民社会や世界に関わっていくことができるようになると確信する。こうした能力 は、しっかりとした教科の基礎的な知識とその知識の背景にある概念についての深い理解 のもとに開発されるべきである。 2.数学的活動の充実 「次期」における算数・数学科の要点は数学的活動と統計的内容の充実であり([11])、ここで は、数学的活動の充実に焦点を当て、統計的内容の充実も視野に入れて検討する。そして、従 前の改訂で課題とされた、 〔算数的活動〕と〔数学的活動〕の位置づけにおける「ずれの解消」
-12-
�
- ▲TOP
 学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第1巻) 学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)