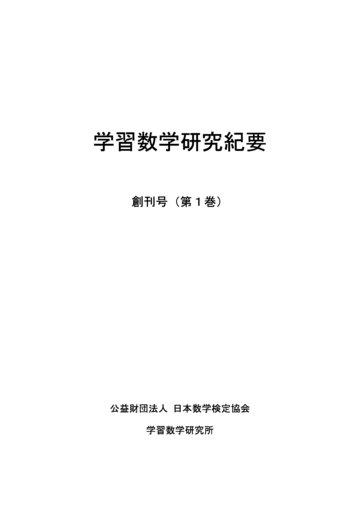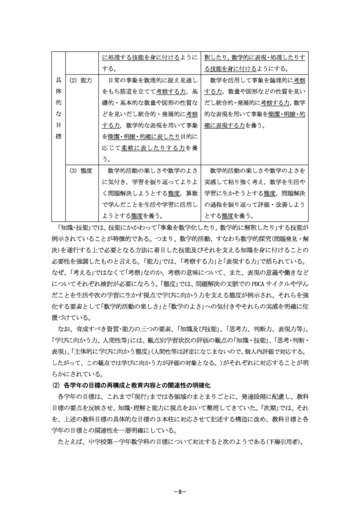学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
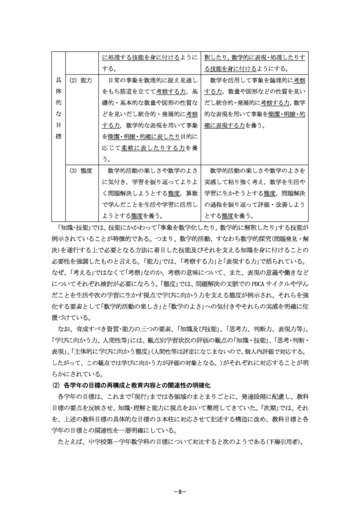
- ページ: 11
- に処理する技能を身に付けるように する。 具 体 的 な 目 標 (2) 能力 日常の事象を数理的に捉え見通し をもち筋道を立てて考察する力,基 礎的・基本的な数量や図形の性質な どを見いだし統合的・発展的に考察 する力,数学的な表現を用いて事象 を簡潔・明瞭・的確に表したり目的に 応じて柔軟に表したりする力を養 う。 (3) 態度 数学的活動の楽しさや数学のよさ に気付き,学習を振り返ってよりよ く問題解決しようとする態度,算数 で学んだことを生活や学習に活用し ようとする態度を養う。
釈したり, 数学的に表現・処理したりす る技能を身に付けるようにする。 数学を活用して事象を論理的に考察 する力,数量や図形などの性質を見い だし統合的・発展的に考察する力, 数学 的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的 確に表現する力を養う。
数学的活動の楽しさや数学のよさを 実感して粘り強く考え,数学を生活や 学習に生かそうとする態度,問題解決 の過程を振り返って評価・改善しよう とする態度を養う。
「知識・技能」では、 技能にかかわって「事象を数学化したり, 数学的に解釈したり」する技能が 例示されていることが特徴的である。つまり、数学的活動、すなわち数学的探究(問題発見・解
決)を遂行する上で必要となる方法に着目した技能及びそれを支える知識を身に付けることの
必要性を強調したものと言える。「能力」では、「考察する力」と「表現する力」で括られている。 なぜ、「考える」ではなくて「考察」なのか、考察の意味について、また、表現の意義や働きなど についてそれぞれ検討が必要になろう。 「態度」では、 問題解決の文脈での PDCA サイクルや学ん だことを生活や次の学習に生かす視点で学びに向かう力を支える態度が例示され、それらを強 化する要素として「数学的活動の楽しさ」と「数学のよさ」への気付きやそれらの実感を明確に位 置づけている。 なお、育成すべき資質・能力の三つの要素、「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、 「学びに向かう力、 人間性等」には、 観点別学習状況の評価の観点の「知識・技能」、「思考・判断・ 表現」、 「主体的に学びに向かう態度」(人間性等は評定になじまないので、 個人内評価で対応する。
したがって、この観点では学びに向かう力が評価の対象となる。)がそれぞれに対応することが明
らかにされている。 (2) 各学年の目標の再構成と教育内容との関連性の明確化 各学年の目標は、これまで「現行」までは各領域のまとまりごとに、発達段階に配慮し、教科 目標の要点を反映させ、 知識・理解と能力に視点をおいて整理してきていた。「次期」では、 それ を、上述の教科目標の具体的な目標の3本柱に対応させて記述する構造に改め、教科目標と各 学年の目標との関連性を一層明確にしている。 たとえば、中学校第一学年数学科の目標について対比すると次のようである(下線引用者)。
-8-
�
- ▲TOP
 学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第1巻) 学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)
学習数学研究紀要 創刊号(第1巻)